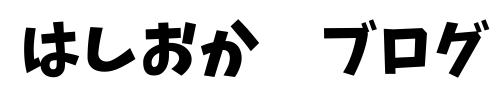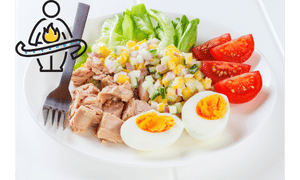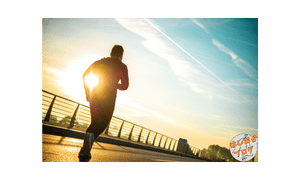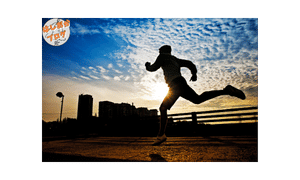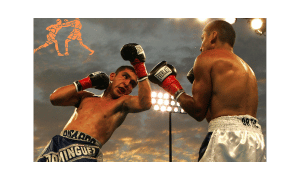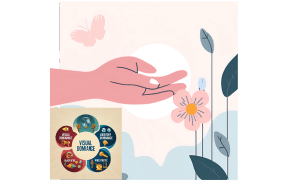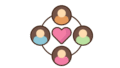僕は、視覚優位。
明らかに僕は、視覚優位です。図で考え、図で全体像を捉え、図で覚えるタイプです。僕自身で「僕は、視覚優位だ。」と自覚したことがあります。それは、高校生の頃のことです。世界史を選択していた僕にとってヨーロッパ史は、それぞれの国の関係を教科書や資料を読んだだけでは理解できない難解な内容でした。様々な国の盛衰が激しく国の名称も人物の名前もなかなか馴染みのない覚えにくいものだったのです。そこで、国と国との相関関係がわかる簡潔な図にまとめてみたのでした。それを毎日よぅく見ることをずっと続けました。するとあら不思議、試験の際、そのまとめた図が思い出され、あれは、あの図のあの辺りのことだから、この選択肢はないなとか、この出来事とこの出来事は同年代だからありうることだなと判断することが容易になって、満点近い点数を取れました。
図で全体を捉え、考える
はっきりとは覚えていませんが、算数や数学でも図とか絵に表しながら考え、解いていたように思います。中学生の頃の娘や息子に数学を教える時でも、数式とともに、図を用いてまず自分で考えて、図で教えていたように思います。子どもたちがわかったようだなという手応えはつかめたのですが、どうでしょう、一応顔を立ててわかったふりをしてくれていたのかもしれません。
視覚優位?聴覚優位?体感覚優位?
自分では、聴覚優位ではないつもりでした。けれど、人の話や声を聴くのは好きです。僕の生活にポッドキャストは欠かせません。情報源としても、人の声を感じるツールとしても僕にとって大事です。無意識で人の話を聞いていると、その内容を鵜呑みにしてしまい、素直にその通りに行動しようとするところがあります。聴いた内容に感化され影響されやすいところがあるのでしょう。とすると、これもある程度当てはまる。
体感覚優位という言葉もあるようです。体を使って実行してみないと理解できない、納得できない。「ん?あれ?これも当てはまってるところがあるぞ。なになに?」
全て当てはまる?
聴覚の文化で優れているなぁと思うのは、時代による変化をあまり感じないことです。録音されたものの音質という点では、時代を感じますが、歌声の素晴らしさは、素晴らしいものはいつまでも素晴らしい。僕は、ジャズもブルースも大好きです。シャンソンも好きです。ジブリ映画を思い出します。令和の歌謡曲も好きです。(ミセスグリーンアップルの歌も素敵ですね。)良いものは良い。
視覚の文化でも、画質の違いはあれど、良いものは良いのですが、眼に映る分、時代や粗雑さを感じさせられてしまうところはあります。自宅に戻ったときくらいしかテレビは見ません。時折昭和の頃の懐かし映像が流れます。画面の比率が違うためでしょう。両脇が黒い映像も流れます。カラーではなく白黒の映像が流れることがあります。それだけで、時代を感じてしまいます。映像に映るコンテンツよりも、時代が眼についてしまうところがあります。それが、視覚文化なのかもしれません。
体感覚優位は、体を動かしながら、実践しながら学んでいくタイプのようです。やはり思い浮かぶのは、アスリートでしょう。また、フットワークの軽い人物も思い出されます。動きながら学ぶ賢い人物を想像します。
聴覚優位かなぁ
詳しい同僚に聞くと、視覚優位は、言葉を次から次へと繰り出すお話好きなのだそうです。うぅん、僕には当てはまらない気がする。
聴覚優位は、ボツボツと物事の本質を捉えたような言葉の使い方をするそうです。本質を捉えられてるかどうかは別として、これが近いかなぁ。
体感覚優位は、体のどこの筋肉を使って、どのように体を動かすことで、機能的にプレーできるかが考えられる人のように思います。考えられるから、「まずは、体を動かしてやってみよう。」となる。そういう心がけは大切だと思っていますが、僕には、運動の楽しさを感じられるけれど、あまり細かいところまでは考えられない。これは当てはまらない気がする。
どれもが当てはまるようなところがあるのだけれど、ずっと視覚優位だと思ってきたけれど、僕はもしかして聴覚優位なのかもしれない。映画を見ている最中に話しかけられるのが、体の芯に堪えるほどストレスでした。ストーリーが断ち切られるように感じるのです。ラジオを聴いているときにも同様です。「今、いい話だったのに。何いってたかわかんなくなったじゃんか。」そういう思いは、いっぱいしてきました。
そうか、僕は聴覚優位だったんだ。ただ、学びには視覚優位が覚えやすいタイプのようだぞ。
自分を振り返る貴重な時間でした。
読んでいただき、ありがとうございます。良い1日になりますように。