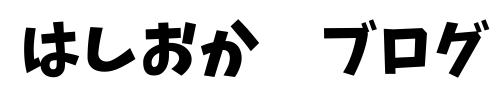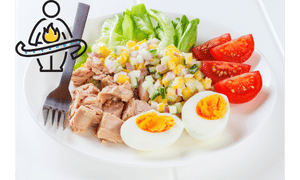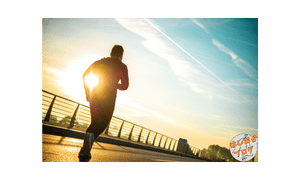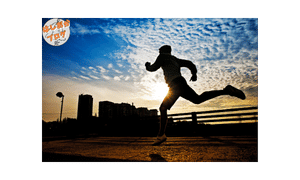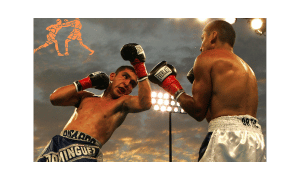映画「みんなの学校」を観てから、学校について考えています。いろいろな個性や特性を持つ子ども達が学習し安心して生活している大阪市立大空小学校。評判を聞きつけ、よその学校から転校してくる子どももいるそうです。中には、前の学校では受け入れられなかったから、大空小学校に転校し、その子が通えるまでになっている。もちろんそこまでの経緯は、生ぬるいものではないけれど、みんなが学校に受け入れられて生活している。そういうわけで、大空小学校には、不登校も問題児もいない。「みんなの学校」を見てから、初代校長の木村泰子さんの著書全て読みました。やはり考え方が素晴らしいなぁと感動します。どこでどのように、あのようなマインドセットを身につけたのだろう。人を深く見つめて、本当の思いやり優しさってなんなのかを鋭く分析でき、それを実現する理想を描ける方なのだと思います。木村泰子さんの著書を引用しながら、学校の魅力を考えたいと思います。
楽しい学校 面白い学校
「勉強がわかって楽しい。」「授業が面白い。」「友達と遊んだり、会話するのが楽しい。」など、子どもたちにとって楽しく、面白い学校が子どもたちにとって一番です。シンプルで簡単なようだけれど、これを達成できるのは難しいだろうなぁということは、容易に考えられます。
- みんな仲良く楽しくの難しさ
いろいろな子どもがいて、その中で生活をします。自分のことを振り返ってみても、やはり嫌な奴はいました。嫌なことを言う人、する人、それをわざと集団でする人。靴隠しとかの嫌がらせもありました。そこで学ぶ世の中の現実もありますが、みんなが仲良く生活するというのは、やはり学校という小さい集団生活の中でも難しいだろうと思います。モンスターペアレントというのでしょうか、学校生活でのトラブルを肯定的に受け止められない親と教育観や子ども観に難のある教員が絡んでくるとさらに困難なことになりそうです。
- 面白い授業の創造
先生の授業力には差があります。私の祖父母は、「今年のお前の先生は、ベテランでいがったなぁ。若いのは、わがね(ダメだ)。」なんて言っていました。授業には、教える内容を熟知するだけでなく、集団をまとめて積み重ねる経験が必要なのでしょう。昔は、保護者の中にも若い先生を育てる雰囲気があったように思います。今は、即戦力として求められるところがあるのでしょう。
自分がされて嫌なことは人にしない、言わない。
大空小学校のたった一つの約束です。学校は、学ぶ場です。人と人との付き合い方も、適切に学ぶ場です。10年後の社会で、孤立しないよう、依存しないよう、上手に人間関係の距離感をとって生活することは大事な学びです。大空小学校の約束は、これ一つ。他にはないそうです。これならば先生方も子どもたちも、保護者たちも共有してみんなで気をつけていくことができそうです。大空小学校の魅力の秘密は、こんなところにあるのかもしれません。
「あいつ邪魔」と人を排除しない
私は職場や地域で、「言っても聞かないから、響かないからあいつに言うのやめた。」「あいつは、無視しよう。」なんて考えてしまうところがあります。少なからず多くの人たちも似たようなところはあるのではないでしょうか?誰かとこそこそとそんな嫌な雰囲気を出している方々もいますし、いわゆる飲み会などでは、そんな悪口大会になる場面に多く出くわしてきました。自分一人でそんな人と割り切って距離を置いたり、誰かと一緒に共闘体制をとったり、何れにしても穏やかな安心した生活には、お互いなりません。
大空小学校では、差別も排除もしません。木村泰子先生は著書の中でこんなことを書いています。『「あいつがうるさくて授業に集中できへんねん。」と言われたら、どう答えるでしょう。「そんなん言ったらあかんよ。」と言う大人の思いやりは、排除の論理です。「ねぇねぇ、その子って迷惑をかけようと思ってやってるの?それとも、困っているの?どっちなんやろうね。」と問いかけてみてはどうでしょう。』問いかけられた子は、対話をしながら、別の考え方に気付き、自分の視野が広がり深くなるような思いがすることでしょう。そんな考え方ができる小学生が、10年後、20年後、地域で生活するようになれば、きっとその地域は素晴らしい土地になる。そんな将来の希望さえ感じさせられる教育方針です。
子どもたちと対話を通して、子どもたち自身が創る学校
言われたことを言われた通りにできることの良さや素晴らしさは、あると思います。日本の伝統的な師弟関係などは、まさにそうだと思います。以前、私自身護身術を教わっていたこともあり、「守・破・離」の考え方を学びました。「言われたことを言われた通りに」というのは、いわゆる「守」の大切さです。社会全体に「守」の下地があれば、秩序正しく治安の良い世の中の基礎となることでしょう。
木村先生は、この多様化の進む世の中で、それだけでは危ないと警鐘を鳴らしています。現在世の中は、戦争や株価下落、物価上昇、不景気等で揺れ動いています。生活もままならない状態で、年々厳しくなっていくのを感じています。誰も経験したことのない光景が近い将来現れるかもしれない。その時に、言われたことしかできない人間、自分で考え行動できない人間は危うい。確かにその通りです。
人を思う優しさと厳しい洞察力を持って、予測不能の時代に生きる子どもたちを思い、子どもたちに問いかけて、子どもたち自身が学校を作るように促していく。そんな学校は、時代の要請にも合致し、魅力的な学校です。
次回その2では、木村先生が考えている子どもたちに身につけてほしい力について考えたことを魅力ある学校と合わせて綴ってみようと思います。
読んでいただき、ありがとうございます。良い1日になりますように。