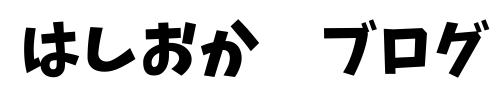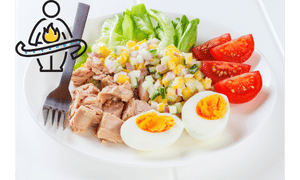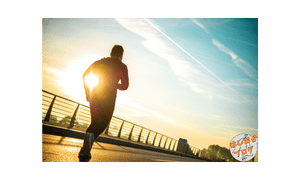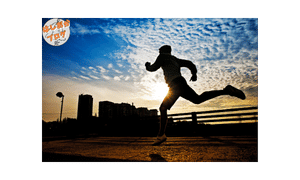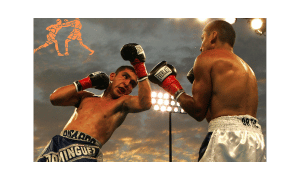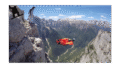仕事を教えるということ
若者に、仕事を教え、育てるということの難しさを感じます。年齢上、若者を多方面で指導する機会が少なくありません。今携わっている仕事をアカデミックな感じで伝えなければならない場面もあります。この年齢になってみて、これまで何となぁく、何となぁく…、でこなしてきた仕事って多かったのだなぁと思うことがあります。うまく言葉で説明できないことが意外に多くあるのです。
人材を育成する上で、不都合な事実 4選
人材育成を任せられ、悩み多き日々を送っている方々も多いのではないでしょうか。「職場には、心理的安全性が大事だ。1on1を取り入れよう。」などと言われるたびに、新しい概念を勉強し、自分が経験して来なかった考え方やみたこともない手法を、改善のイメージがないままに、成果も見込めないまま導入し、経験の裏打ちがなく実感の伴わない実戦ばかりが世の中に広まっていく感じがあります。(心理的安全性って何だろう?)
教わって来なかった
自分が若い頃は、教えてくれる人などいませんでした。教育プログラムもありませんでした。見て覚えろ!でした。「見て覚えられん奴は使えん。」そう言われているような気がして、一生懸命に見て学んだものです。周りの先輩たちのやり方を見たり、比較的年齢の近い方に聞いたりして覚えました。そして、体当たりのようにぶつかりながら、間違いながら、恥をかきながら覚えていった感じです。そう考えると、たくさん迷惑をかけながら学ばせていただきました。
時代の変化による職場風土の違い
若い頃は、叱られました。厳しい指摘を受けたりしました。不条理なことも多々ありました。けれど、飲み会などもありざっくばらんに様々なことを話す機会がありました。20年ほどしか立っていませんが、今はそんなことができません。叱るにも、言葉を選ばなければなりません。飲み会に無理に誘うのもダメなのだそうです。つまり、自分がされてきたやり方で教えようは、封印されているのです。
自分のやってきたことが、通用しない
職場内だけではなく、世の中が大きく変化しました。コロナ禍を経て、さらに価値観が急速に変化していると感じます。自分がこれまで成果を出してきた手法が、ここ数年に管理職に非難されるのを聞くと、自分の中に具体的に伝える仕事のやり方もエピソードもほとんど残っていないのを感じます。今の世の中でよしとされているやり方を、ちょっぴりの経験とそこから膨らませる理屈で実感の伴わない伝え方をする他ないのです。
わかったような顔をして聞く若者
人の話を聞くときに、ふざけた態度であれば、厳しく指摘されました。裏でネチネチと言われることもありました。今は、「こちらが時間を割いて話してんだろうが!」と思わず言いたくなるような態度の若者もいます。言葉を選ばないといけないので、ぐっとこらえて考えます。「なんて言おうかしら??良い言い回しはあるかしら??」そんなことを考えているうちに、6秒がたちアンガーマネジメント成立です。怒りも落ち着き、まぁいいやと、流してしまうのでした。
やってみせるが一番伝わるのだろうが…
なんだかんだと言っても、やってみせるのが一番伝わると思います。何事もそうですが、「わかる」と「できる」は、別物です。やって見せて、それが実際に成果があることを見せた方が、イメージが残り、身につけやすいはず。でも、残念ながら僕には、現在の潮流にあったやり方ができていないことと、やる機会がないことから、やってみせることはほとんどできていません。
学び直しだと思って割り切る
自分がやってきたやり方にこだわりすぎたり、若者への対応の仕方が時代とともに変わったことを嘆いても何も変わりません。やはり自分が、時代についていくべく変わらなければならない。様々な書籍を読んだり、それを実践して少しずつ経験を積んでいく。
人材育成の手法について、過去から真似ることも学ぶことも、あまり期待できない現状。僕たちの年代は手探りで新しいやり方をつかむことが宿命づけられた年代なのかもしれません。
若者を育てることは、この国の文化を維持することにつながります。さらに、頼もしい若者たちがさらに良い日本へと発展させてくれる希望も個人的にはもっています。人材育成は、国家の存亡に関わる大きな仕事です。
一生涯を前向きに、学び続けよう。時代の変化に合わせて、自分を変えていこう。そんな風に実践し努力する姿を実際にやってみせ、なんらかの良い影響が若者に伝わることも期待して。
読んでいただきありがとうございます。良い1日になりますように。